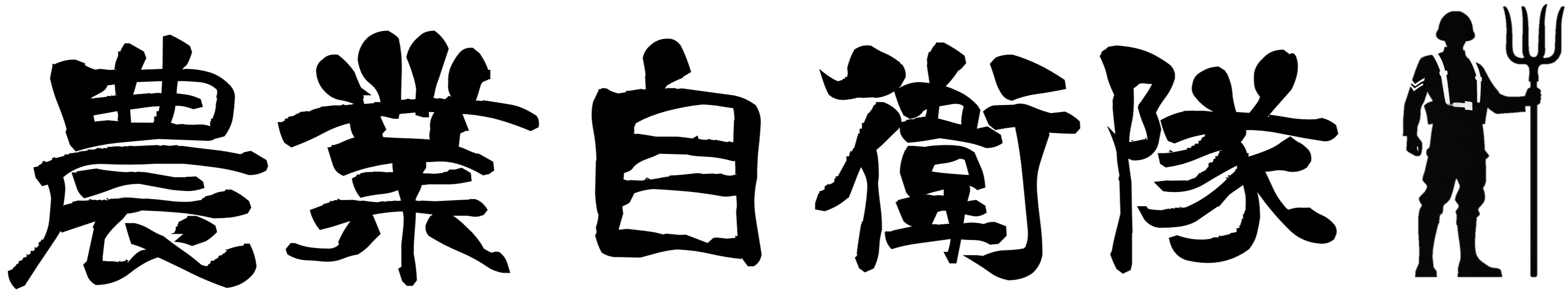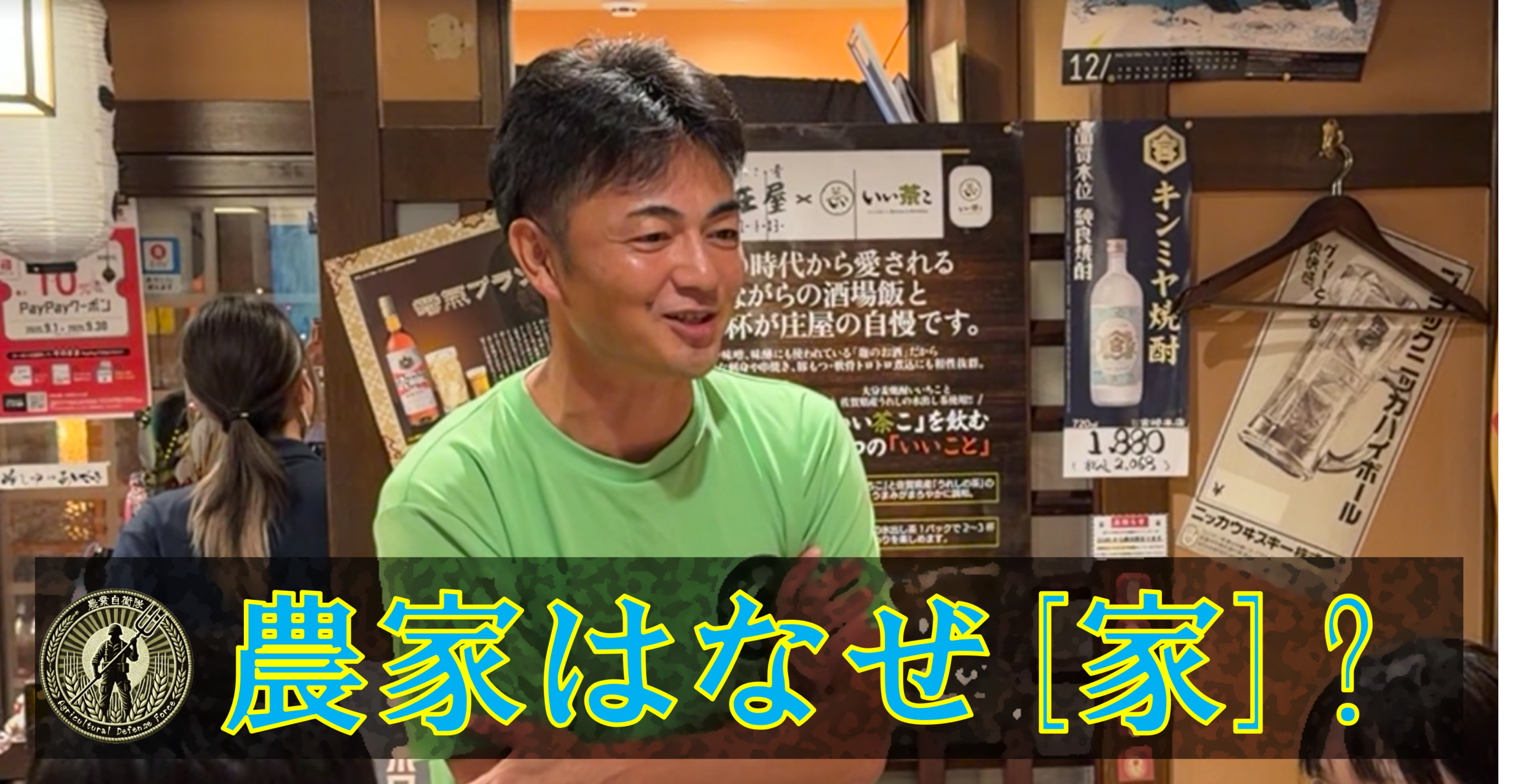米先任!宗谷南JAの皆さまと日本農業新聞の皆さまと席を同じくしたであります!マイナビの出会いからご縁がつながり、現場の課題と可能性を率直に語り合えたであります!
よい流れじゃな。動いて会いに行く者に道はひらけるのう。


北海道でも人手不足は深刻で、退職自衛官の体力と規律に期待があると伺ったであります!退職年齢の56歳でも“若手”として現場の戦力になれる手応えを感じたであります!
受け入れの段取りまで含めて設計することじゃ。住まい、季節就労、研修の導線を一体で整えるのう。


「農家」という名に宿る歴史を尊びつつ、新規参入の扉を開く合図として「農師」を併存させる発想にも触れたであります!作物を“作品”と見る視点にも学びがあったであります!
言葉は文化を映す鏡じゃな。礼を失わず、扉を広げる。名乗りと実績の両輪で進むのう。


農業自衛隊らしい呼称案として「農尉」「農曹」「農士」もいいのではないかと考えたであります。
名に恥じぬ働きを積み重ねよ。北海道の圃場にも足を運び、実地の協働計画を形にするのじゃぞ。

ごあいさつ
この度は、北海道宗谷南JAの皆さまと、7月に記事にしていただいた日本農業新聞の皆さまと、一席を共にしました。不思議なご縁ではありますが、私たちが参加したマイナビ「新・農業人フェア」で宗谷南JAの皆さまとつながり、その後のご紹介で日本農業新聞の取材へと発展。本日は北海道から都内にお越しの折にお声がけいただき、貴重な時間をご一緒することができました。
全国課題と北海道の現場感
人手不足の深刻さと“若手”としての退職自衛官
全国的に同様の課題がありますが、北海道でも人手不足は深刻。体力・規律・継続力を備える退職自衛官の参入は「大変心強い」との共感をいただきました。地域の若手が就農に向かわない一方、他地域から志をもって就農する動きも見られるとの肌感を共有いただき、「農をやりたい」退職自衛官は頼もしい戦力として受け止められていることを実感しました。
「農家」という呼称をめぐって
歴史と文化が宿る“家”の字
印象に残ったのは、「農家」という呼び名をめぐるやり取りです。
「家の字には、家族単位で継承されてきた歴史と文化が宿る。」
まさにその通りだと感じました。
一方で、そのことがクローズドな文化を生み、新規就農者からは「コミュニティにどう入ればよいかわからない」という悩みも。そこで、漁師にならう形で「農師」という呼称を併存させる発想が提案されました。言葉そのものが壁ではないにせよ、文化の層が言葉に表れることを踏まえ、文脈に応じて「農家」と「農師」を使い分けるのは、伝統を尊びつつ扉を開く合図になり得ると感じました。
「農家」を“芸術家”のように
加えて、「農家」を芸術家(陶芸家・画家など)のように飛躍させるという視点も共有されました。援農の現場では、農家さんごとに作業手順や選果基準のこだわりが明確で、同じ作物でも最終の姿が違って見えることに気づかされます。そこには技術を超えた表現が息づき、「作物は“作品”」であると実感します。ゆえに、農を“芸術”にたとえる視点は比喩にとどまらず、営みの本質を射抜くものだと考えています。
農業自衛隊らしいネーミングの遊び心
議論はふくらみ、私たちからは「農尉」「農曹」「農士」といった呼称の案も。
たとえば「1等農曹」少し遊び心も交えつつ、誇りと役割を言語化するアイデアとして盛り上がりました。
学びと認識の共有
農は国策、国民全員の課題
会は大いに盛り上がり、改めて農は国策であり、国民全員の課題であることを再確認しました。食料安全保障・環境・雇用・文化の継承いずれも暮らしの基盤です。私たちは、多様な入り口を整え、多様な担い手を受け入れる仕組みづくりが欠かせないと考えています。
結びに
宗谷南JAの皆さま、そして取材をしてくださった日本農業新聞の皆さま、このたびは貴重なご縁を結んでいただき、心よりありがとうございました。農業自衛隊は、農業界のみならず日本が抱える多様な課題に真摯に向き合い、持続可能で幸せな未来の実現に向けて、これからも力強く歩みを進めてまいります。