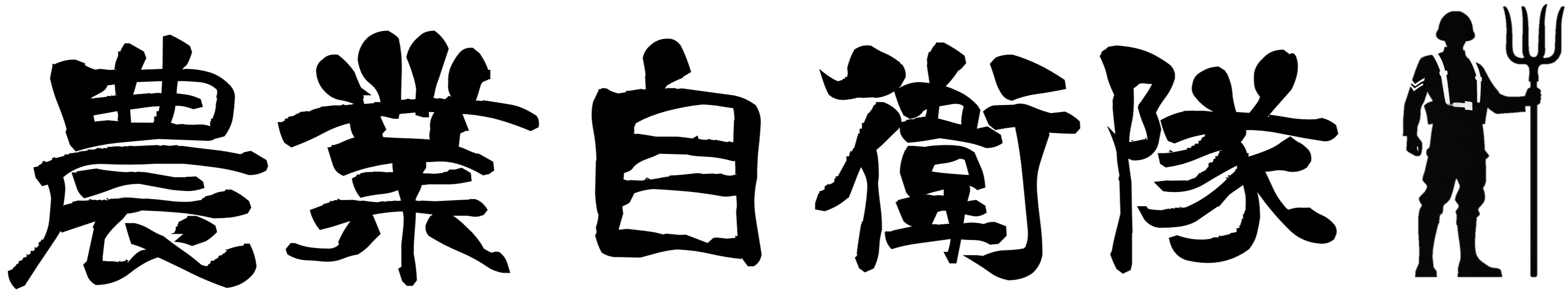FoodBox株式会社 代表・中村圭佑さんと農業自衛隊で懇親会を開催しました。
この懇親会は、ただの意見交換ではなく、「我々はどこから来て、どこへ向かうのか」を問う、熱く真剣なものとなりました。
中村さんは、中国で1000ha級の農地を軍と協働しながら運営した経験をはじめ、タイ・ベトナム・インドなどで農業を“空間的”に広く捉えてきた方です。

同時に、農地改革や学校給食制度の設計思想といった“時間軸=歴史”にも深く通じています。
そんな「時間と空間の両方から農業を見てきた」実践者の言葉は、まさに私たち農業自衛隊に必要な視点ばかりでした。
「一人では無理でも、仕組みとチームなら実現できる」
「農業を日本の目線だけで考えるな」
「評論で終わらせるな。行動で示せ」
「歴史を学ばずして、未来は語れない」
どの言葉も、刺さるというより、背中を強く押されるような感覚でした。
特に強く印象に残ったのは「歴史の文脈を理解したうえで、今の農業を再設計する」という視点です。
農地改革、JA制度、学校給食の背景。
こうした制度のルーツを知らずに、いまの農業を“改善しよう”としても、土台が揺らいでしまう。
我々は「構造そのものを理解すること」から逃げてはならないと再認識しました。
また、中国での“分業制×機動部隊型”の農業構造。
田植え部隊・収穫部隊・防除部隊のように役割を細分化し、効率と継続性を両立させる仕組み。
これは、私たち農業自衛隊が考える“農業のタスクフォース化”と高い親和性があり、非常に参考になりました。

さらに、心に残ったのは「感性と文化としての農業」という話です。
虫の音や風鈴の音を“意味ある音”として受け取る民族は、世界でも日本人くらい。
この感性は、単なる文化的誇りではなく、「農」に深く根ざした、世界に誇るべき“美意識”なのだと。
だからこそ、農業はただの生産活動ではなく、「暮らし」や「文化」とも連動して設計し直す必要がある。
そしてそれを“感性レベル”で理解できる私たちだからこそできる農業がある。
この話には、どこか誇りのようなものを感じました。
今後は、それぞれの地域が持つ環境や資源の個性に寄り添いながら、持続可能な形を模索するスキームの構築に取り組んでいきます。自然の循環と人の営みをつなぎ、時には外の世界からも学びを得ながら、実践と対話を重ねていきたいと考えています。
中村さんの人間力、それは、戦略を語れる“理”と、現場で泥をかぶる“情”の両立にあります。
私たちはこの姿に心から共鳴しました。
評論では終わらない。
動く。
語れる。
繋げる。
それが農業自衛隊の“これから”です。
中村さん、ありがとうございました。