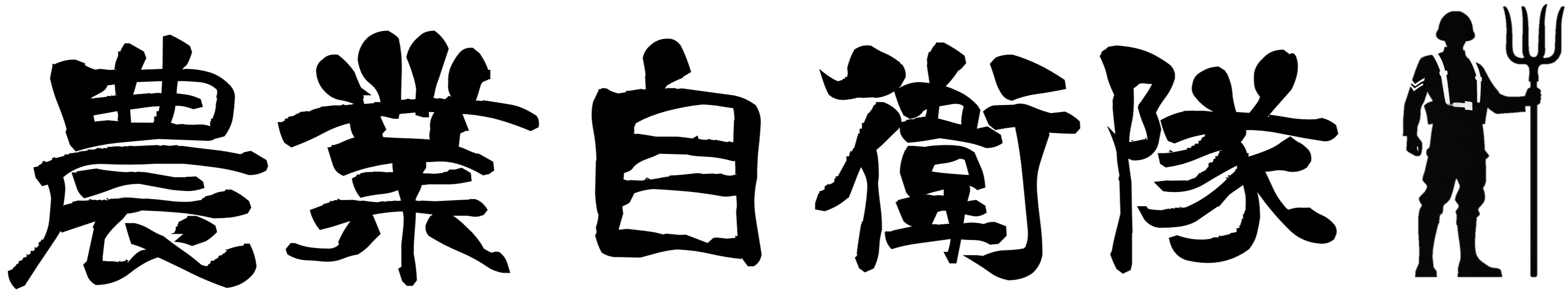※画像はイメージです。
「氷点下でもトマトが実る!?」――火山の恵みで北極圏に“常夏”をつくる革新的ハウス
冬の平均気温が0 ℃前後のアイスランドで、一年中25 ℃の温室が稼働しトマトやキュウリが鈴なりになる――その秘密は地熱エネルギーをフル活用した地熱温室農法。今回は、アイスランドのトマト専門農園 Friðheimar(フリズヘイマル)様を参考に、システムの仕組みと有事対応力をストーリー仕立てで紹介します。
1.ごあいさつ
前回の「江戸時代ニシン肥料農法」に続き、第3回は北欧アイスランドから 地熱温室農法。国土の火山帯から湧く熱水と再エネ電力を組み合わせ、国内野菜の約半分をグリーンハウスで供給する循環型モデルです。
Point! 化石燃料に頼らず寒冷地でも高収量を実現するこの仕組みは、日本の寒冷・豪雪地域や有事用の自給温室としても応用可能です。
2.地熱温室農法とは?
2-1 誕生の背景
- 地熱資源大国:アイスランドの一次エネルギーの54 %が地熱由来、住宅暖房の約90 %も地熱で賄われています。
- 温室の歴史:最初の地熱温室は1923年に温泉町フヴェラゲルジで建設。町は今や“温室の都”として知られます。
- Friðheimarの登場:1995年に家族経営でスタートし、現在は5,000 m²の温室で年間約370 tのトマトを生産(アイスランド国内シェア15〜18 %)。

2-2 仕組みのキモ
- 加温:地下100 ℃前後の熱水を配管循環し、室温20〜25 ℃を維持。暖房コストは化石燃料比90 %削減。
- 照明:冬期は最大17時間/日のLED/HPS照明を地熱電力で稼働し、光合成量を確保。
- CO₂施用:近隣地熱発電所から排出される火山性CO₂を温室に導入し、光合成効率を平均15 %向上。
- 培地殺菌:栽培ごとに熱水スチームで溶岩砂培地を消毒し、化学薬剤を極小化。

3.システムを覗いてみよう
| Step | 要素 | コツ |
| 1 | 地熱井パイプ設置 | 温水配管は床面と側壁の二重ループで温度ムラを抑制 |
| 2 | 高断熱二重ガラス | 外気−5 ℃でも内側結露を防ぎ、日射利用効率を最大化 |
| 3 | LED自動調光 | 外光センサー連動で電力を20 %節約 |
| 4 | CO₂循環 | 植物群落CO₂濃度を800–1,000 ppmで自動制御 |
| 5 | 観光連携 | 温室内レストランで規格外トマトを加工提供し廃棄ゼロ |
4.ここがスゴイ!地熱温室のメリット
- 超省コスト
熱・電力とも再エネ自給で、EU平均比で光熱費1/3。 - 低炭素フードマイレージ
トマト1 kg当たりCO₂排出は欧州露地物の25 %。 - 高収量
露地比6〜8倍/m²の収穫量、キュウリは国内自給率100 %。 - 観光・雇用創出
Friðheimarは年間13万人来訪、地域最大の雇用源。
5.「有事対応力」こそ最大の魅力
- 燃料・電力自給型:地熱井+発電で外部エネルギーに依存しない。停電時も温室機能を維持。
- 寒冷・積雪地でも適用:北海道や東北の温泉地に導入すれば、冬期の生鮮供給拠点に。気温−1.3 ℃のレイキャヴィークと同条件で実証済み。
- 災害食料備蓄の代替:LEDとCO₂施用で短期多収型リーフレタスも可能。
6.まとめ 〜“氷と火”が育む常夏オアシス〜
「火山の熱が野菜を実らせ、野菜が地域を温める」
地熱温室農法は、再生可能エネルギー・高収量・有事対応を同時に満たす先端モデルです。日本の寒冷地や温泉地で応用すれば、エネルギー自給と食料安全保障を両立する“北国版グリーンリボン”となり得ます。
次回は、世界の農法シリーズ#4「ザイ農法(西アフリカ・サヘル地方)」を取り上げる予定です。ぜひ、お楽しみに!✨
参照文献・ウェブ資料
Friðheimar公式サイトForsíða | Friðheimar
CN TravelerCondé Nast Traveler
Mother Earth Newsマザーアースニュース
ThinkGeoEnergyThink GeoEnergy – Geothermal Energy News
Statistics IcelandStatistics Iceland
HortiDailyHortidaily
NatHab Blogナチュラルハビタット アドベンチャーズ
Orkustofnun資料Forsíða — Orkustofnun
Energy in Iceland(Wikipedia)Wikipedia
Atlas ObscuraAtlas Obscura
Back to the Roots BlogBack to the Roots Blog
Cartogramme TravelCartogramme