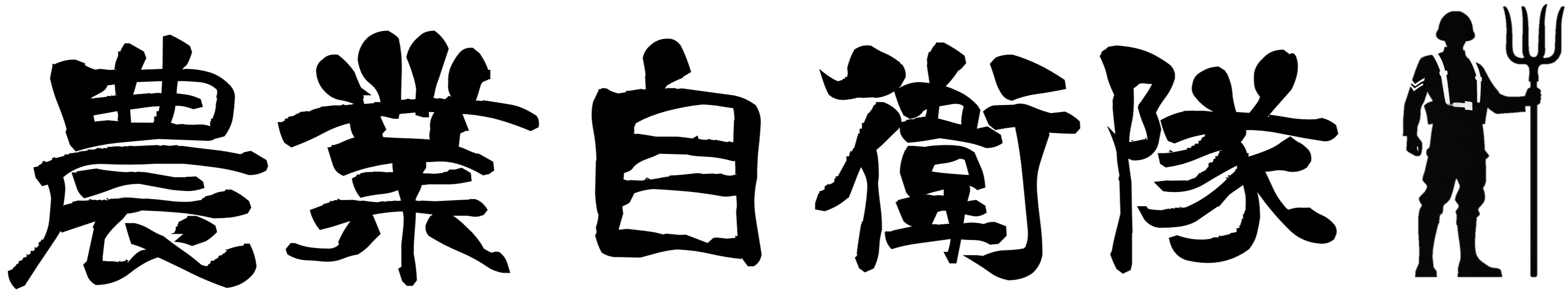#2「江戸時代のニシン肥料農法」
1.ごあいさつ
前回の「菌ちゃん農法」に続き、今回は江戸時代に北海道(蝦夷地)で隆盛を極めた ニシン肥料農法 を取り上げます。大量に獲れるニシンを煮沸・圧搾して油を搾り、残渣を乾燥させた 鰊粕 が“肥料の王様”として西日本へ船で運ばれ、田んぼに撒くだけで収量が激増した――そんなダイナミックな循環型農業の物語です。
2.北海道でニシン漁が大ブーム
- 北海道沿岸では 18〜19 世紀に刺網・地曳網が導入され、ニシン漁が爆発的に発展。
- 春の産卵期には浜が銀色に染まるほどの「群来(くき)」が見られ、漁期のピークには 一漁場で千人規模が従事 した記録も残ります。

3.鰊粕の製造と威力
| 工程 | 概要 | 効果・特徴 |
| ①煮沸 | 直径 1.8 m の大釜でニシン約 1,000 尾を 30 分煮る | 脂肪分を溶出させる |
| ②圧搾 | 木製「角胴」やネジ式「キリン」で油を搾る | 搾り滓が黄金色の鰊粕に |
| ③乾燥 | 巨大な干場で細かく砕き数日天日干し | 軽量・長期保存が可能 |
| ④輸送 | 北前船に積み、大坂・瀬戸内・九州へ | 金肥として高値取引 |
一反(約 10a)につき 20 貫目(約 75 kg)の鰊粕を元肥に入れると、稲や綿の出来が「無類」と称されるほど飛躍した と豪農の日記に記録されています。
4.西はニシン、東はイワシ――魚肥文化の東西分布
- 西日本(近畿・中国・四国)では、北海道産の鰊粕が大量に流入し、米・綿・菜種の主力肥料に。
- 東日本(関東・東北)では、地元で獲れるイワシを乾燥させた 干鰯 が主流。“安価で即効性が高い”と評され、房総の九十九里浜などが一大生産地に。
- 18 世紀後半、干鰯相場高騰が農民一揆(国訴)を招くと、安価な鰊粕が注目され、西日本へ急速にシフトした経緯があります。
5.収量アップのメカニズム
- 高タンパク&即効性窒素
魚粕は分解が早く、根が直ちに窒素を吸収できるため 登熟期の黄化を防止。 - リン酸・カルシウム豊富
籾数と登熟率が改善し、江戸期の稲作は平均反収が 2〜3 割増 と報告。 - 有機酸で土壌改良
油分の残渣が団粒構造を整え、水田の還元障害を緩和する副次効果も。
6.社会・環境インパクト
- 経済効果:鰊粕は「無類粕」と呼ばれ、金肥市場で最高値を記録。西日本の綿花バブルを支えた。
- 環境負荷:一方で大釜燃料の大量伐採が北海道西岸の森林を急速に消失させたとの報告も。
- 労働問題:漁場ではアイヌをはじめ多くの労働力が酷使され、民族社会に大きな影響を与えた。
7.現代へのヒント
化学肥料が主流になった現代でも、魚粕はオーガニック農家の間で「即効性と土壌活力を両立する資材」として再評価が進んでいます。有事の自給力向上 と 地域循環型農業 を掲げる農業自衛隊としては、当時の知恵を現代技術と掛け合わせることで、サステナブルな“第三の魚肥ルネサンス”を提案できるでしょう。

まとめ
江戸時代のニシン肥料農法は、海の資源・物流・農業が結びついた究極の循環モデルでした。北海道の豊漁が西日本の田畑を潤し、東日本ではイワシが地域自給を支えた――そのスケールと創意は、資材高騰や供給不安を抱える現代こそ学ぶ価値があります。